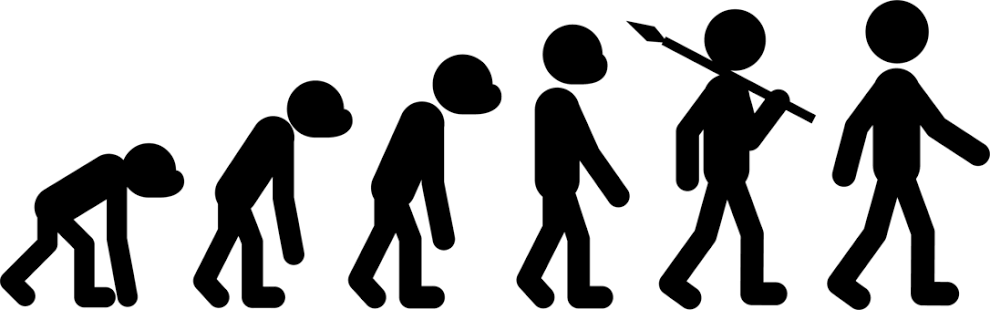なぜか最近、ヒト族の歴史に惹かれてる。
こんにちは^^のびおです
ここ最近、やたらと「ホモサピエンス」と「ネアンデルタール人」の話に惹かれるようになったんですよね。
別に昔から歴史マニアってわけでもないし、理系の考古学畑の人間でもない。でも、なんかこう…「私たちはどこから来て、なぜ今ここにいるのか?」って問いが、妙にリアルに迫ってくる感覚があるというか。
きっかけは、あるドキュメンタリーを観たことだった。
ホモサピエンスとネアンデルタール人は、約4万年前まで共存していたという。そして今、地球上に残っているのは私たちホモサピエンスだけ。
「なぜ彼らは滅びて、私たちは生き残ったのか?」
この問いがずっと心に引っかかって、気づけば本を読んだり論文をあさったりしていた。
そして、ふと思ったんですよね。
この違いって、現代人が抱えている“生きづらさ”や“自律神経の乱れ”とも、どこかでつながっているんじゃないか?って。
今日は、そんなことをちょっとだけ深掘りしてみようと思う。
ネアンデルタール人とホモサピエンスの違いって?
まず大前提として、ネアンデルタール人は決して“劣った種”ではなかった。
脳の容量はむしろホモサピエンスより大きかったし、狩猟技術や火の使用、道具の工夫、死者を弔う文化さえあった。身体もがっしりしていて、寒冷地にも強かったと言われてる。
じゃあ、なぜ彼らは絶滅してしまったのか?
いくつかの有力な説がある中で、私が興味を惹かれたのは「環境への適応力の違い」っていう視点。
たとえば、ホモサピエンスは少人数のグループで柔軟に移動しながら生活していたのに対し、ネアンデルタール人はわりと定住的な暮らし方だったとか。
気候変動や生態系の変化が起きたとき、臨機応変に動けたのはホモサピエンスの方だったんだろう。
つまり、「状況に合わせて自分を変化させる能力」こそが、生き延びる力だったとも言える。
現代人の“脳”にも受け継がれたもの
面白いことに、ホモサピエンスの脳って、「現状維持」を好むようにプログラムされてるって言われてるんです。
危険を避けるために、変化よりも安定を選ぶ。それはつまり、“命を守るため”に最適化された思考パターン。
「このままで大丈夫かな?」って不安に思ったり、「失敗したらどうしよう」って考えちゃうのも、本来はサバイバルに役立つ機能だったんだと思う。
だけど、それが現代のように情報が溢れていて、刺激過多な社会になるとどうなるか?
脳はずーっと興奮モード、つまり交感神経優位になりやすくなる。
「なんとなくずっと緊張してる」
「深く眠れない」
「常に考えすぎてる」
こういう感覚を抱えている人、私の周りにも本当に多いです。
これって、もしかしたら“サバイバル脳の暴走”なのかもしれないって最近思うようになったんですね。
もっと「人本来の感覚」に従っていい
ホモサピエンスは変化に適応する能力に長けていた。それは事実。
でももうひとつ、彼らが持っていたであろう力って、「感覚に素直であること」じゃないかとも思う。
お腹が空いたら食べる。
疲れたら眠る。
不安を感じたら群れで寄り添う。
そこには、無理に“がんばる”とか、“ちゃんとしなきゃ”みたいな強迫観念はなかったと思うんです。
ところが現代では、
「食べたら太るから我慢しなきゃ」
「休んだら置いていかれるかも」
「不安でも笑顔でいなきゃ」
…みたいに、感覚よりも“思考”が優先される社会になってしまった。
だけど本来、私たちの身体ってものすごく優秀。
体温を調節してくれるし、ウイルスが入れば免疫反応が起きるし、ストレスがかかれば涙まで出してくれる。
この“身体の声”をもっと信じて、耳を傾けてもいいんじゃないかなって思う。
最後に、のびおからの一言。
ホモサピエンスが生き残ったのは、環境に合わせてしなやかに変われたから。
でもその“柔軟さ”って、何も「考え抜く力」だけじゃなくて、「感じて動く力」でもあったと思う。
自律神経が乱れてしまう現代社会で、私たちができることって、
実はもっとシンプルかもしれない。
考えすぎてしまうなら、考えなくても大丈夫な時間を意図的につくる。
うまくいかない日があっても、「まあ、今日はそういう日だった」って流してみる。
それって、ホモサピエンスが受け継いできた“生きる知恵”でもある気がしてならない。
だから今日も、深呼吸をひとつして、自分の身体に問いかけてみてほしい。
「ねえ、今、ほんとはどう感じてる?」
そんな問いかけから、人生は少しずつ、しなやかに変わっていくと思うんだ。
皆さんが少しでものびのびした生き方ができますように。
人生一度きり、楽しんでいきましょ!